
タイ料理店の扉を開けたとき、またはバンコクの街角で、あの芳醇な香りに包まれた経験はありませんか。その香りの正体が、タイの食卓に欠かせないタイ米、特にジャスミンライス〈Khao Hom Mali〉です。日本のお米とは異なる食感や風味を持つため、「炊き方が難しそう」「失敗を防ぐにはどうすればいい?」と不安に感じる方も多いかもしれません。
この記事では、初めてでも安心してタイ米をパラパラに炊き上げる方法を、日本の炊飯器を使った簡単な手順から、本場の味を再現する水加減、そして現地のコツまで徹底的に解説します。この記事を読めば、ご自宅でいつでも現地の雰囲気あふれる本格的なタイ料理を楽しめるようになります。

タイ国政府観光庁が認める「タイランドスペシャリスト」の資格を持ち、渡航歴50回以上、現地滞在10年以上を誇る「まさよし」が、本記事を執筆しました。長年の経験と現地で得た生きた情報に基づき、最新かつ正確な情報をお届け。タイの文化、食、マナーまで、あなたのタイ旅行を安心で充実したものにする専門家として、信頼性の高い情報提供に努めています。
詳しいプロフィールは「コチラ」をどうぞ!
この記事でわかること
- 失敗しない炊き方 日本の炊飯器を使ったタイ米の最適な水加減(1:1.05)と手順がわかり、調理の失敗を防ぐことができます。
- 現地のコツとマナー タイ米は「研がない」「浸水しない」という現地の雰囲気を重視した基本的なマナーと理由が理解できます。
- パラパラ食感の実現 伝統的な湯取り法の具体的な手順がわかり、お店のようなパラパラとした食感を再現できます。
- 品種の違いと特徴 ジャスミンライスがタイ料理に最適である理由と、日本米との決定的な違いが把握できます。
- 香りの引き出し方 炊き上がりの**「蒸らし」と「ほぐし」**の裏技を知り、タイ米の豊かな香りを最大限に引き出すことができます。
- 炊いた後の活用法 炊き上がったタイ米を使った定番レシピや、ベタついた際のリカバリー法など、時間を有効に使うアレンジ術がわかります。
👇このあとの目次から、気になる項目をすぐにチェックできます。ピンポイントで知りたい情報がある方は、ぜひ活用してください。
タイ米(ジャスミンライス)とは?日本米との決定的な違い

この章では、タイ米の代表格であるジャスミンライス(カオ・ホーム・マリ)の基本的な特徴と、日本の主食であるジャポニカ米との違いを解説します。事前にタイ米の性質を理解することで、なぜ独特な炊き方が必要なのかがわかりやすいはずです。
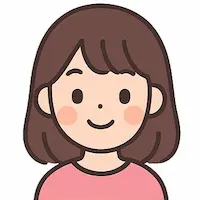
◎「日本米との違いを知ってから調理したら失敗が減った」という声が多数
複数の旅行ブログやSNSの投稿から見えてくる共通点は、タイ米を日本米と同じ感覚で洗米・浸水してしまうと失敗しやすいという点です。実際に訪れた人の口コミでは、「パラパラさせる秘訣は、粘り気の元となるデンプンを洗いすぎないこと、そして水を少なくすることだと理解して、初めて上手に炊けた」という体験談が多く、事前に品種の特性を学ぶことが成功の鍵を握るようです。この知識が、調理の失敗を防ぐことに直結しています。
タイで最も愛される「カオ・ホーム・マリ」の特徴
タイ米の約80%を占めるとされる「カオ・ホーム・マリ」は、タイ語で「香りのよいお米」を意味する最高級のインディカ米です。最大の特徴は、炊飯時に漂う、まるでポップコーンや花のつぼみのような甘く豊かな香りです。粒が細長い長粒米であり、炊き上がりの粘り気が極めて少ないため、一粒一粒が独立したパラパラとした食感になります。この食感が、タイ料理の複雑でスパイシーなソースを邪魔せず引き立てます。
現地での食べ方:タイカレーや炒め物でパラパラが好まれる理由
現地タイでは、ジャスミンライスはカレー(ゲーン)や炒め物(カオ・パット)など、ほとんどの料理のベースとして食されます。パラパラとした食感は、汁気の多いグリーンカレーのソースを吸い込みすぎず、また、具材の多いチャーハンでも米同士がくっつかず均一に混ざるため、料理全体の味のバランスを保つのに適しています。逆に、日本のような粘りのあるお米は、タイ料理の風味を打ち消してしまう可能性があるため、現地の味を再現するにはジャスミンライスが最適です。
【炊飯器で簡単】タイ米の基本の炊き方と失敗しないコツ

この章では、ご家庭にある日本の炊飯器を使って、タイ米を簡単かつ美味しく炊くための基本的な手順と、失敗を防ぐための重要なコツを具体的に解説します。初めてでも楽しめるよう、最もわかりやすい方法をまとめました。
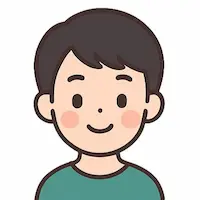
🔸「水加減を間違えてベタついてしまった」と戸惑う人も多く、注意が必要
複数の口コミでは、日本米と同じ目盛りで水をセットしてしまい、粘り気のある失敗作になってしまったという声が散見されます。成功者は口を揃えて「水は米と同量か、少し少ないくらいが良い」「浸水なしで早炊きモードを使ったら上手くいった」と報告しています。このことから、タイ米の炊飯は時間を有効に使い、浸水時間を省略することが、パラパラ感を出すための重要なポイントであることがわかります。
必須の手順:「研がない(さっとすすぐ)」と「浸水しない」理由
日本の米はデンプン質を取り除くために「研ぐ」ことが重要ですが、タイ米、特にジャスミンライスは軽くすすぐだけで十分です。力を入れて研ぐと、米粒が砕けやすくなる上、貴重な香りの成分まで流れ出てしまいます。また、米に水を吸わせる「浸水」も基本的に不要です。インディカ米はジャポニカ米よりも吸水スピードが速く、長く浸水させると粒が崩れたり、ベタついたりする原因になります。洗米したらすぐに炊飯器のスイッチを入れましょう。
黄金比は1:1.05|水加減と早炊きモードの活用
タイ米をパラパラに炊くための水加減の黄金比は、米1に対して水1〜1.1倍です(容積比)。日本の炊飯器の目盛りを使うと多すぎるため、計量カップで正確に測ることを推奨します。炊飯器のモードは、通常のモードではなく、**「早炊き」**モードを使うのがコツです。早炊きは加熱時間が短く、浸水時間も含まれていないため、タイ米の粘りを出さずに、一気に炊き上げるのに適しています。
香りを立たせる「蒸らし」と「ほぐし」の裏技
炊飯が終わった直後も、美味しく炊くための重要なプロセスです。炊き上がりの直後は蓋を開けず、5分から10分間そのまま蒸らしましょう。この蒸らし時間で余分な水分が飛び、お米の中心部まで熱が均一に伝わり、香りが立ちます。蒸らし終えたら、しゃもじで底から大きく十字に切るようにほぐし、余分な水蒸気を逃がしてください。このひと手間で、パラパラ感が格段に増し、現地の雰囲気に近い仕上がりになります。
【本格志向】湯取り法(鍋・フライパン)で作る本場レシピ

より現地の雰囲気に近い、本格的なパラパラ食感を目指すなら、タイの伝統的な調理法である湯取り法(ゆどりほう)がおすすめです。この章では、湯取り法のメリットと、鍋を使った具体的な調理手順を解説し、初めてでも楽しめるよう、プロのコツを盛り込みます。
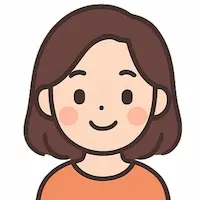
◎「湯取り法で作ったらお店の味に近づいた」という本格志向の声が多い
複数のタイ料理愛好家のSNS投稿では、「湯取り法」で炊くことで、よりパラッとした理想的な食感に仕上がったという報告が目立ちます。特に、チャーハン(カオ・パット)やカオマンガイに使用する米としては最適で、「茹でることで米の余分なデンプン質が落ち、粘りがなくなる」という理由が挙げられています。少々手間はかかりますが、この方法を試すことで、料理のグレードが格段に上がると、時間を有効に使いたい本格志向のタイ料理ファンから支持されています。
湯取り法のメリットと必要な調理器具
湯取り法は、たっぷりのお湯で米を茹でてから蒸す調理法です。この方法の最大のメリットは、茹でる過程で米の表面のデンプンが洗い流されるため、炊飯器で炊くよりもさらに粘り気が少なく、究極のパラパラ食感を得られる点です。必要な調理器具は、大きめの鍋(米が自由に踊る程度の深さがあるもの)、ザル、そして蓋付きの鍋またはフライパンです。
湯切り〜蒸らしまでの具体的な手順
- 茹でる: 鍋にたっぷりの湯(米の10倍程度)を沸騰させ、軽くすすいだタイ米を投入します。時々かき混ぜながら、米の中心にわずかに芯が残る(アルデンテの状態)まで、約8〜10分茹でます。米粒の周りが透き通るのが目安です。
- 湯切り: 茹で上がったらすぐにザルにあけ、しっかりと湯切りをします。ここでお湯を完全に切ることで、米の水分調整を行います。
- 蒸らし炊き: 湯切りした米を鍋に戻し入れ、蓋をして弱火にかけます。鍋底から「パチパチ」という音が聞こえたら、水分が飛んだサインです。火を止め、そのまま10分間しっかりと蒸らして完成です。この蒸らしで、米の中心の芯が取り除かれ、理想のパラパラご飯になります。
炊き上がったタイ米を使った絶品アレンジレシピ

タイ米のパラパラとした食感と香ばしさは、タイ料理だけでなく、様々なレシピで初めてでも楽しめる独特の魅力を発揮します。この章では、基本のタイ料理から、日々の食卓に取り入れやすい簡単なアレンジレシピをご紹介します。
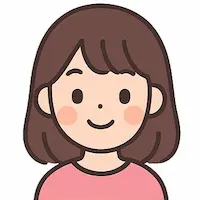
◎「タイ米で作るチャーハンが別格の美味しさ」とアレンジに満足の声が多数
タイ米を炊いた後の活用法として、SNSでは特に「カオ・パット(タイ風チャーハン)」への満足度が非常に高い傾向にあります。日本米でチャーハンを作るとベタつきやすいですが、タイ米を使うことで一粒一粒が独立し、プロのような仕上がりになるとの声が多数です。「余ったタイ米を冷凍しておき、炒飯やカレーの際に時間を有効に使って利用している」という主婦層からの報告も多く、日常の料理で活躍する集合知が形成されています。
定番レシピ(グリーンカレー、カオマンガイ)
- タイカレー(ゲーン): 粘り気の少ないタイ米は、グリーンカレーやレッドカレーなど、サラサラとしたスープ状のカレーとの相性が抜群です。米がソースを吸い込みすぎず、最後までカレー本来の味と香りが楽しめます。炊いた米を平皿に盛り、脇にカレーを添えて少しずつかけながら食べるのが現地の雰囲気です。
- カオマンガイ(鶏のせご飯): 鶏肉の茹で汁で米を炊き込む(本来は鶏油を加える)料理ですが、シンプルに炊いたタイ米に、茹で鶏とそのタレをかけても美味しくいただけます。パラパラのご飯が、タレと鶏肉の旨味をしっかり受け止めます。
簡単レシピ(パッタイの米麺の代用、サラダへのトッピング)
- アジア風ピラフ・チャーハン: 前述の通り、タイ米は炒め料理との相性が最高です。日本のチャーハンよりも油分を控えても、パラパラ感を維持できるため、ヘルシーに調理できます。ナンプラーとライムで風味を加えれば、手軽にエスニックな味わいに。
- サラダやスープの具材: 冷やしたタイ米をサラダのトッピングとして使ったり、ミネストローネなどのスープに加えても、米粒が崩れず、満足感のある一品になります。日本米のお粥とは違う、粒が立ったサラサラの「タイ風お粥(カオ・トム)」にも最適です。
タイ米に関するよくある質問(Q&A)
タイ米の調理法や保存法に関して、読者から寄せられやすい疑問をQ&A形式でまとめて回答します。調理の際の最後の不安を解消し、安心してタイ米生活を始められるようにサポートします。
Q: 炊き上がりがベタついてしまったら?
A: 水加減が多すぎたか、炊飯前に浸水時間が長すぎたことが原因です。ベタついてしまった場合は、すぐに蓋を開けて、しゃもじでご飯を大きく広げ、余分な水分と蒸気を飛ばしましょう。その後、フライパンに少量の油をひいて、焦げ付かないように炒めることで、チャーハンやカオ・パットに活用できます。翌日、乾燥させてから炒飯に使うのも、失敗を防ぐ知恵です。
Q: 炊く前に洗わなくても本当に大丈夫ですか?
A: タイの最高級ジャスミンライスは、精米技術が高く、基本的に洗わなくても問題ありません。むしろ、何度も研ぐと香りが飛んでしまうため、「さっと一度、表面のホコリを流す程度」に留めるのが、現地の雰囲気を重視したタイ在住者の間でも一般的なマナーであり推奨される方法です。
Q: 低GI米と聞きましたが、栄養的なメリットはありますか?
A: ジャスミンライスは、血糖値の上昇を示すGI値(グリセミック・インデックス)が比較的低い「低GI食品」として知られています。インディカ米は、ジャポニカ米よりもでんぷんの構成上、消化・吸収が穏やかであるため、食後の血糖値の急激な上昇を抑えたい方にとって、健康的な選択肢となります。
まとめ
本記事では、タイの食卓に不可欠なタイ米(ジャスミンライス)の炊き方を、炊飯器を使った簡単な方法から、本格的な湯取り法まで解説しました。
重要なのは、「浸水させず、水を少なめに、さっとすすいで炊く」という日本米とは逆の調理法を理解することです。これらの手順を踏まえれば、ご自宅でもパラパラで香りの良い本格タイ米を安心して楽しむことができます。この情報が、あなたの食卓を豊かにし、次の旅への期待感を高めるきっかけになれば幸いです。

